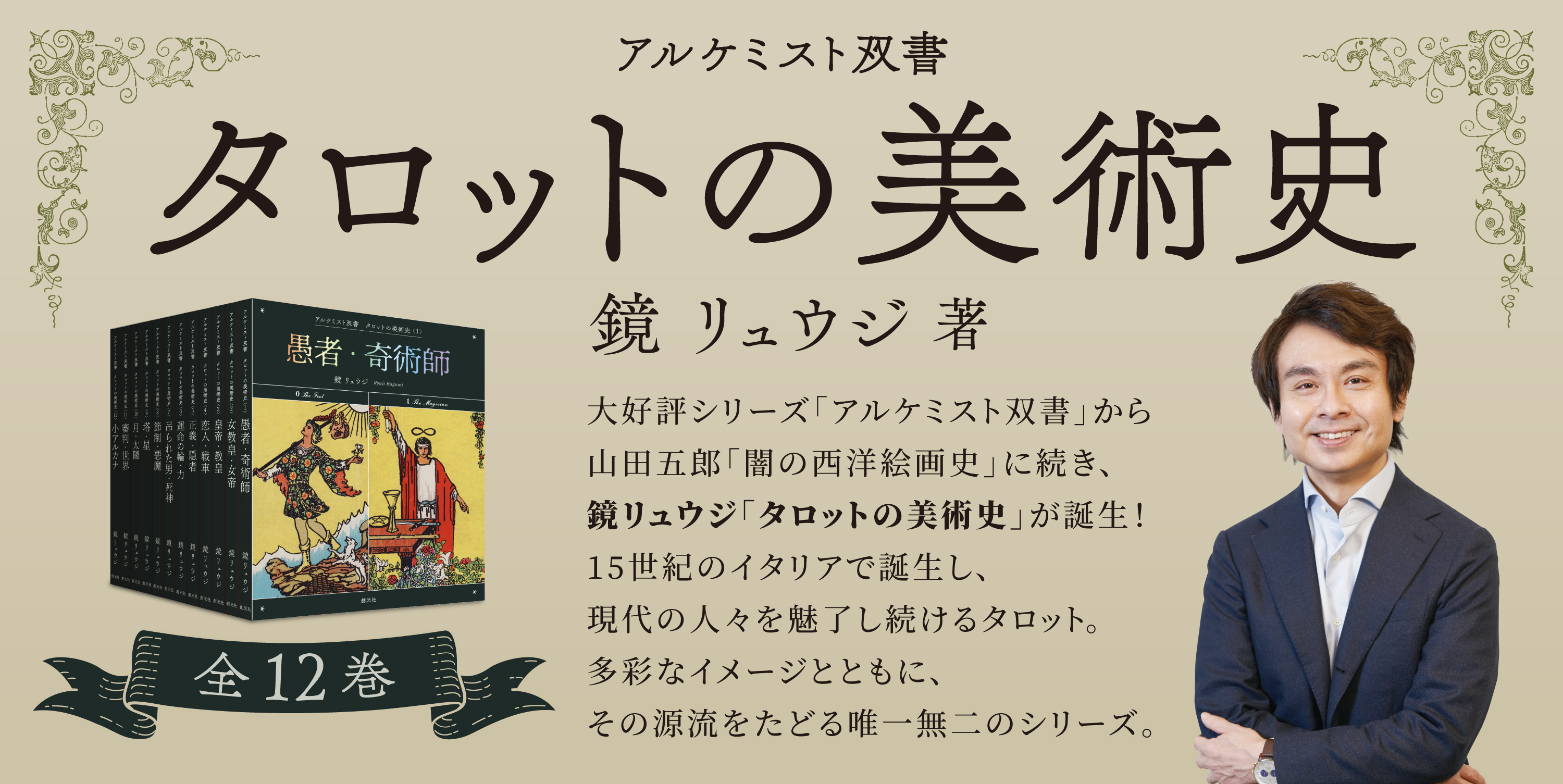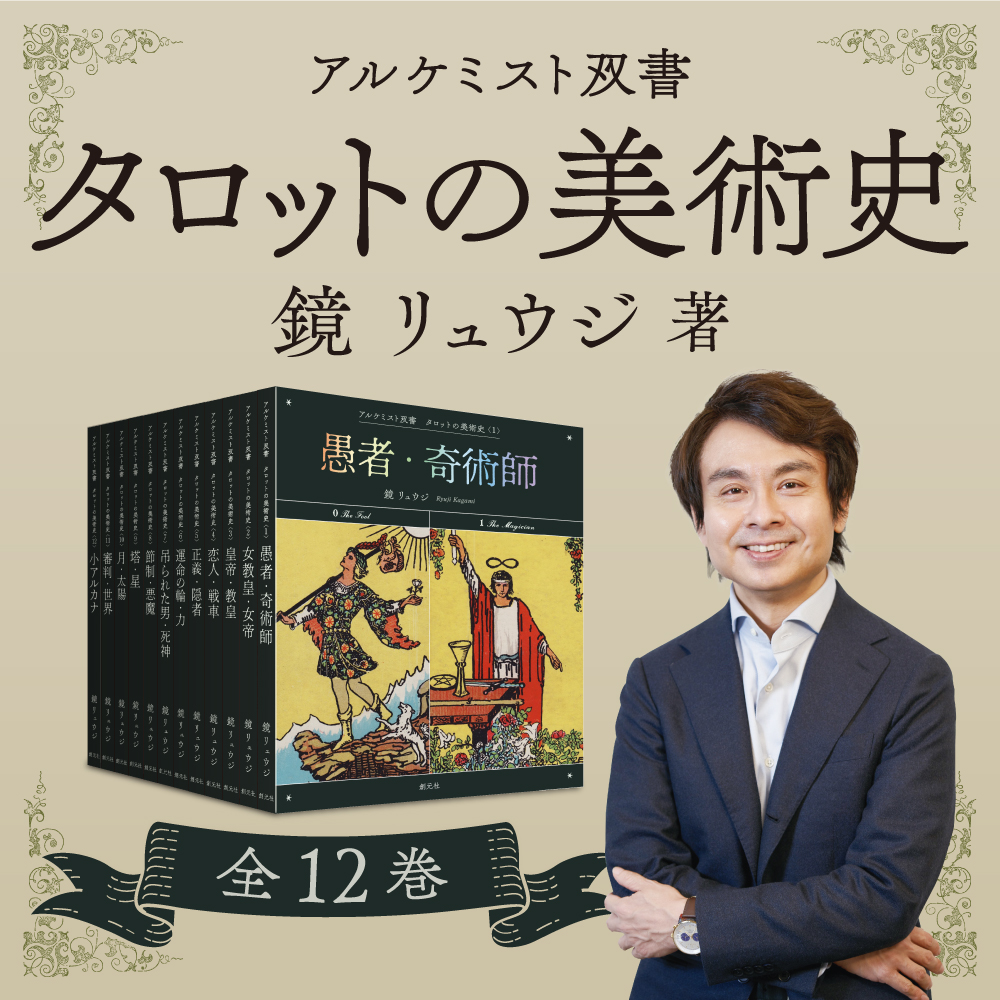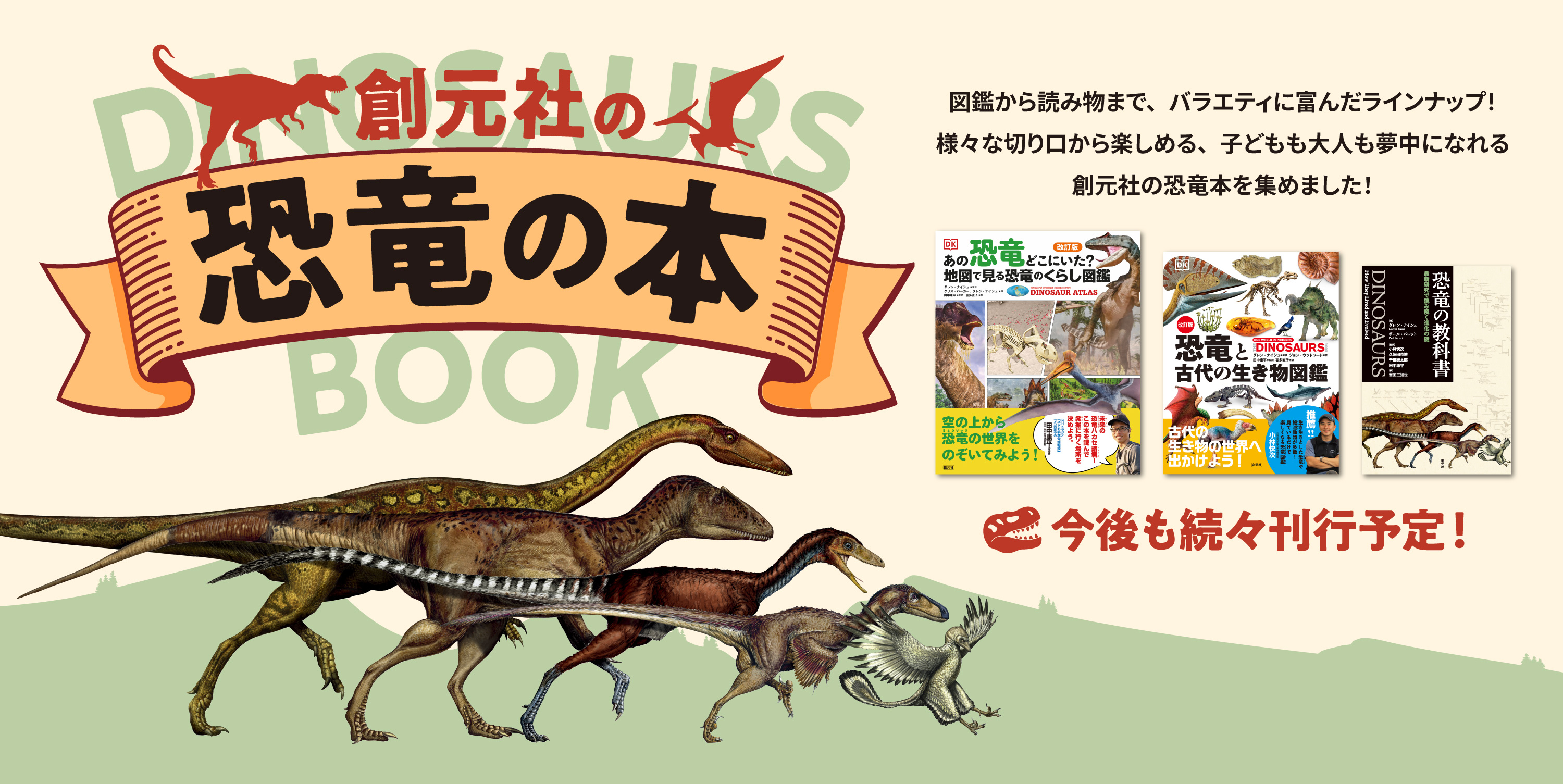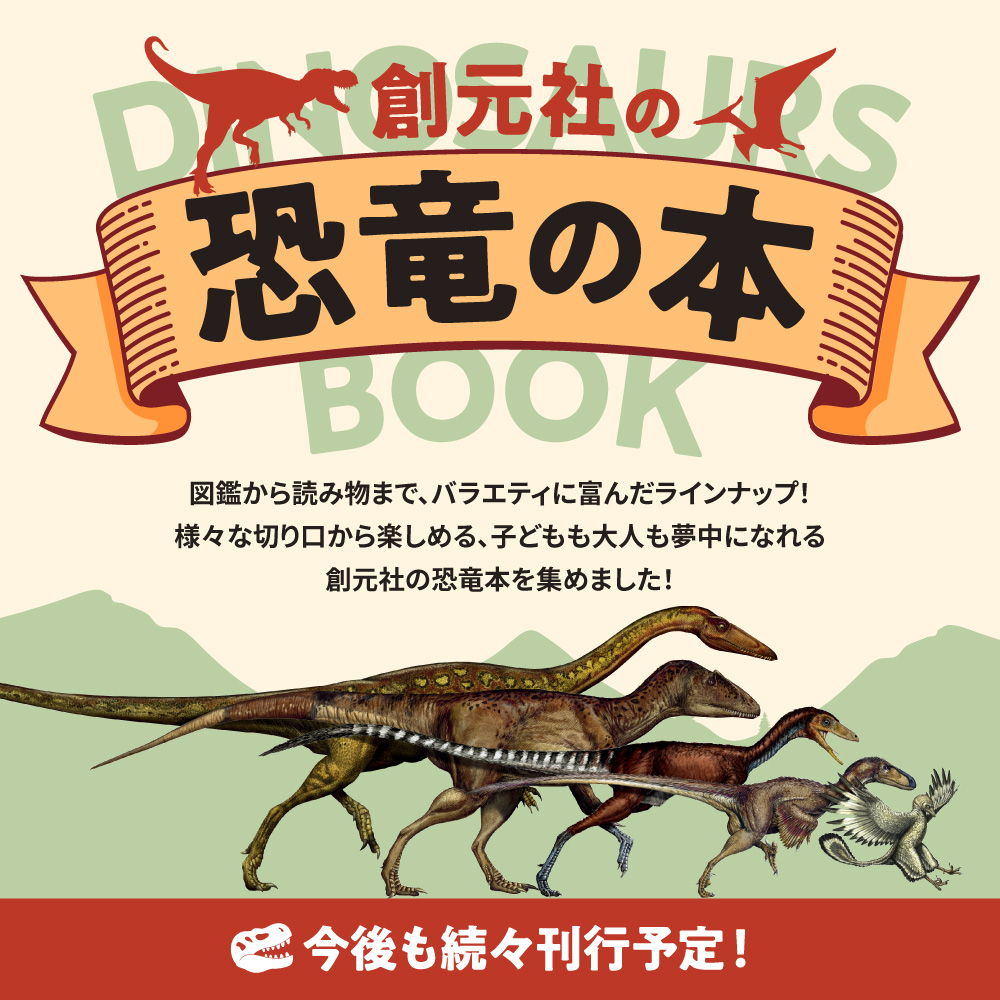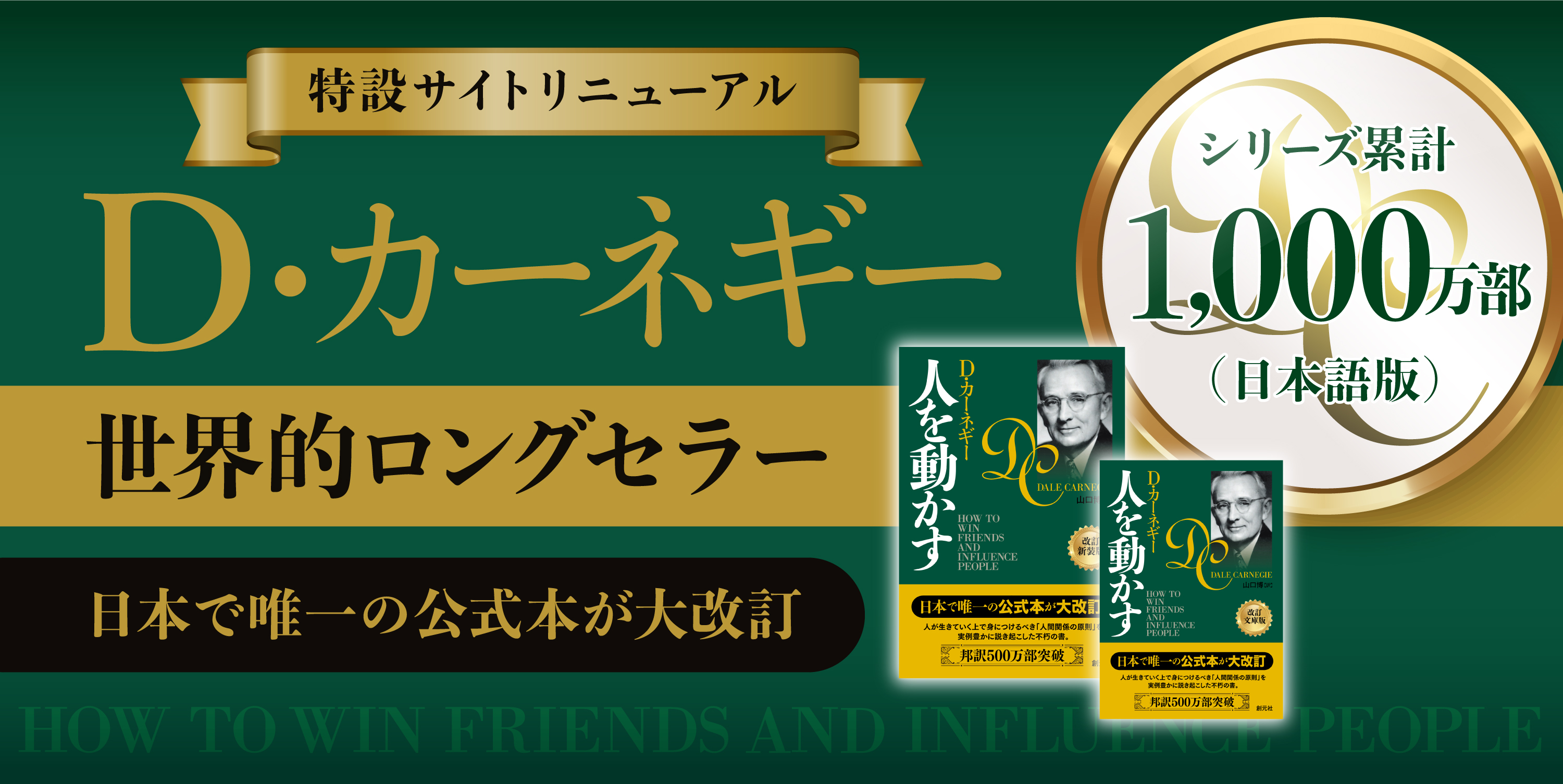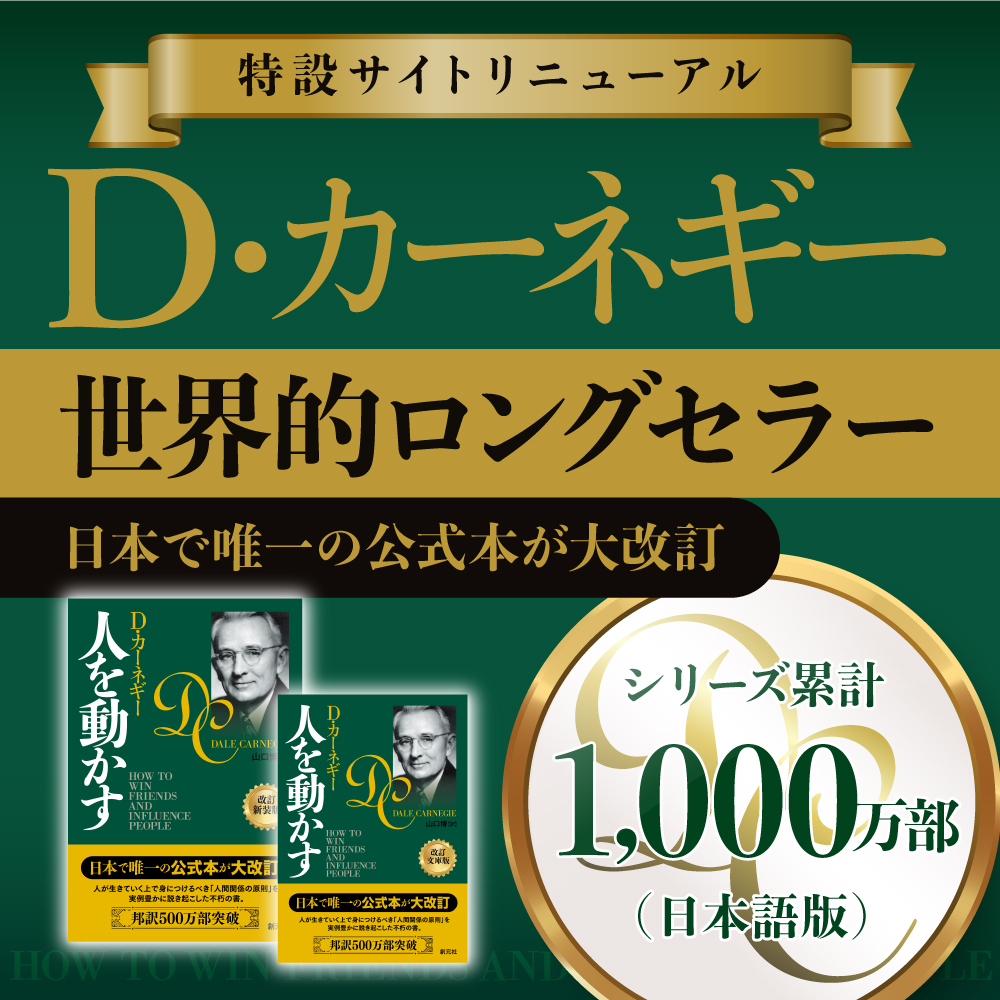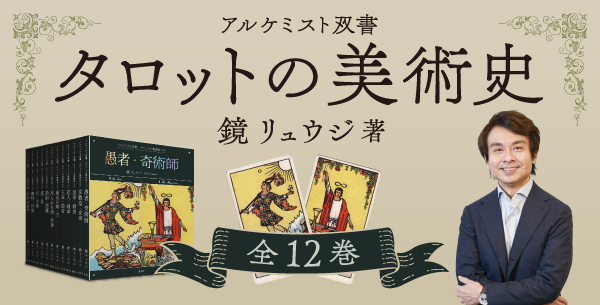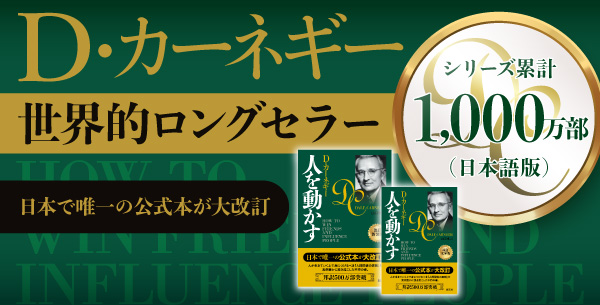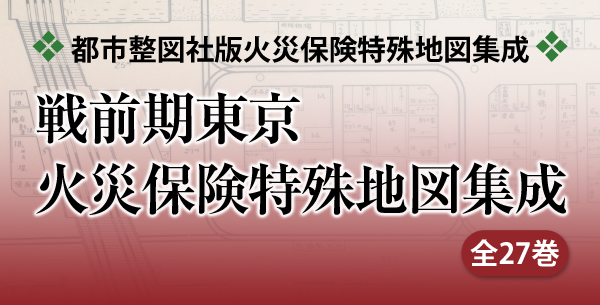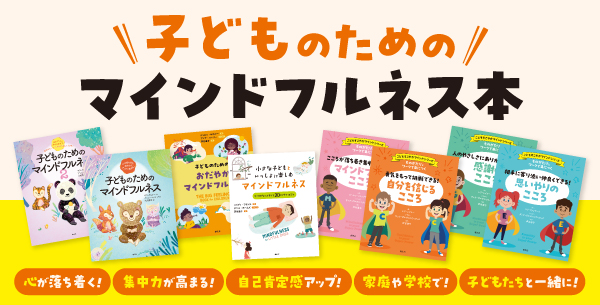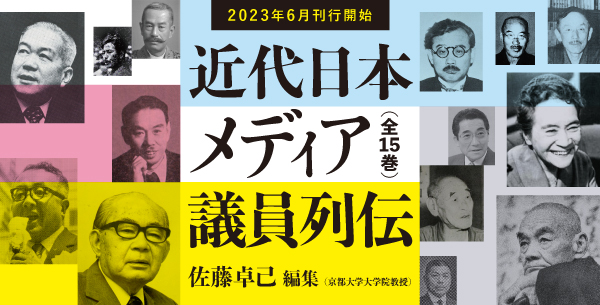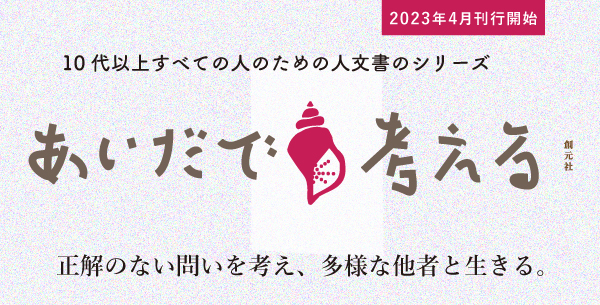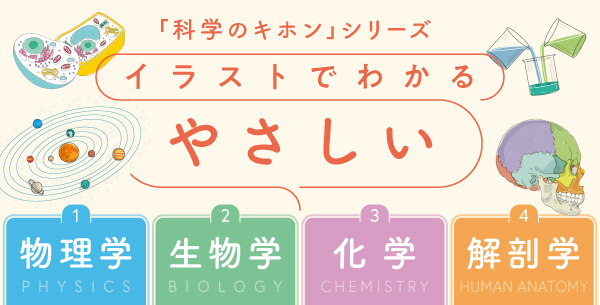発売カレンダー
-
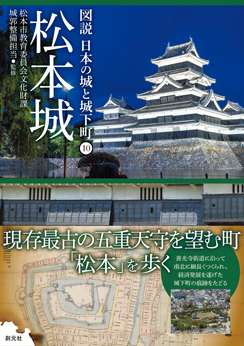
松本城
定価:1,650円
刊行日:2024/04/09
-
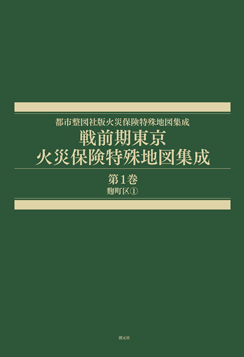
戦前期東京火災保険特殊地図集成 第1巻
定価:110,000円
刊行日:2024/04/09
-

近代日本の別荘建築
定価:3,850円
刊行日:2024/04/09
-
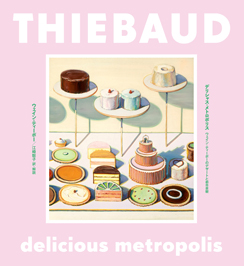
デリシャス・メトロポリス
定価:4,950円
刊行日:2024/04/09
-
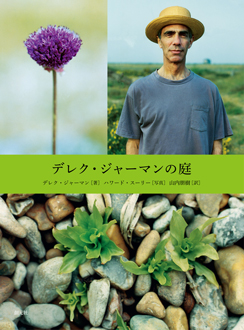
デレク・ジャーマンの庭
定価:4,180円
刊行日:2024/04/09
-
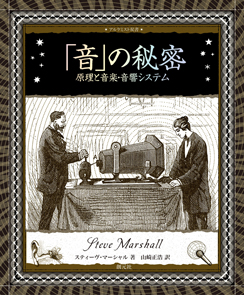
「音」の秘密
定価:1,320円
刊行日:2024/04/16
-
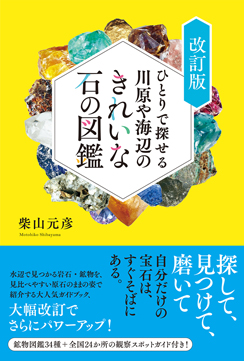
ひとりで探せる川原や海辺のきれいな石の図鑑 改訂版
定価:1,980円
刊行日:2024/04/16
-
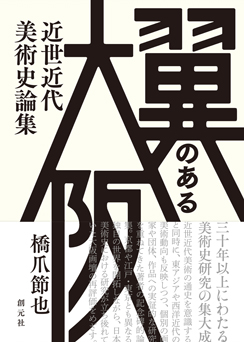
翼のある大阪
定価:6,600円
刊行日:2024/04/16
-
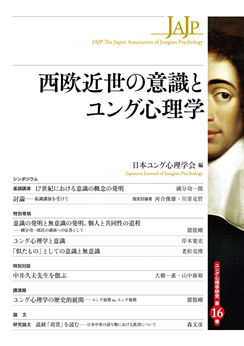
西欧近世の意識とユング心理学
定価:2,200円
刊行日:2024/04/25
-
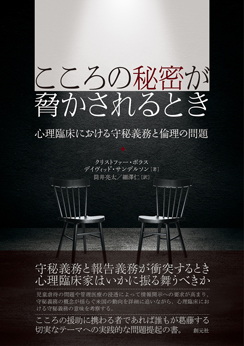
こころの秘密が脅かされるとき
定価:3,960円
刊行日:2024/04/25
-
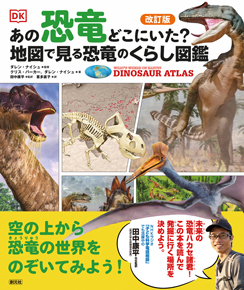
改訂版 あの恐竜どこにいた? 地図で見る恐竜のくらし図鑑
定価:2,970円
刊行日:2024/04/25
-
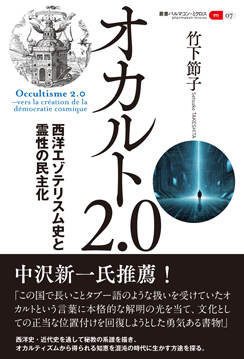
オカルト2.0
定価:2,420円
刊行日:2024/04/25
-

「聖性」から読み解く西欧中世
定価:2,970円
刊行日:2024/05/15
-

戦前期東京火災保険特殊地図集成 第2巻
定価:132,000円
刊行日:2024/05/15
-
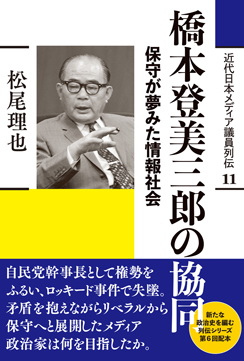
橋本登美三郎の協同
定価:2,970円
刊行日:2024/05/15
-
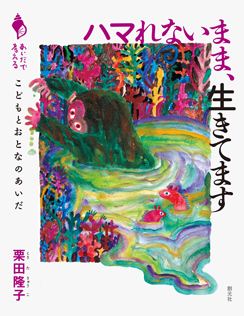
ハマれないまま、生きてます
定価:1,760円
刊行日:2024/05/15
-
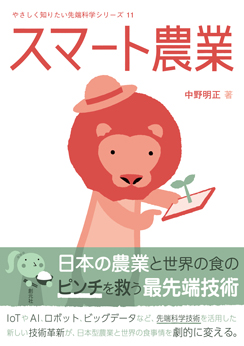
スマート農業
定価:2,200円
刊行日:2024/05/15
-

奇妙で不思議な土の世界
定価:2,420円
刊行日:2024/05/15
-
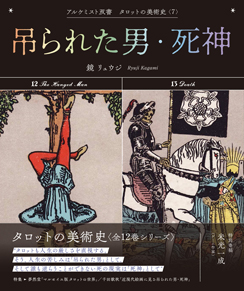
吊られた男・死神
定価:1,650円
刊行日:2024/05/21
-
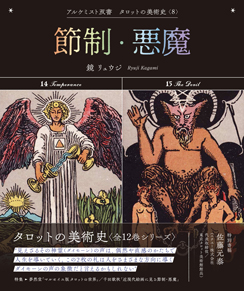
節制・悪魔
定価:1,650円
刊行日:2024/05/21
-

塔・星
定価:1,650円
刊行日:2024/05/21
-

ストレスの歴史
価格未定
刊行日:2024/06/10
-
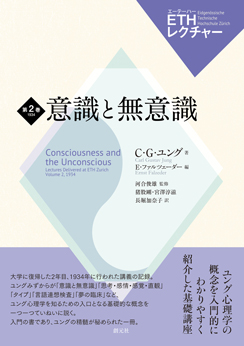
意識と無意識
定価:4,400円
刊行日:2024/06/10
-
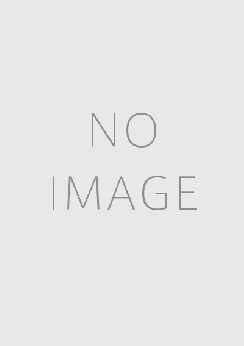
大阪天満宮と天神祭
定価:2,200円
刊行日:2024/06/10
-
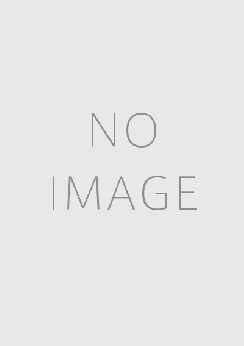
看護・助産師教育に活かすパフォーマンス評価ワークブック
価格未定
刊行日:2024/06/10
-
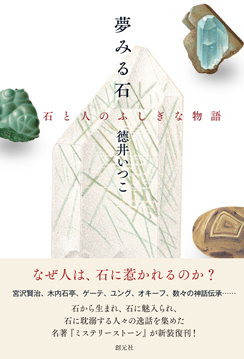
夢みる石
定価:2,420円
刊行日:2024/06/10
-
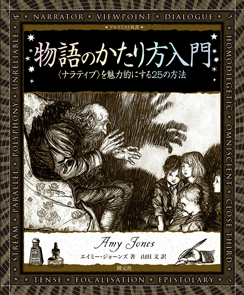
物語のかたり方入門
定価:1,650円
刊行日:2024/06/13
-

戦前期東京火災保険特殊地図集成 第3巻
定価:132,000円
刊行日:2024/06/13
-
![車両の見分け方がわかる! 関西の鉄道車両図鑑[第2版]](/upload/thumb_image/list/mb24107m.jpg)
車両の見分け方がわかる! 関西の鉄道車両図鑑[第2版]
価格未定
刊行日:2024/06/13
-
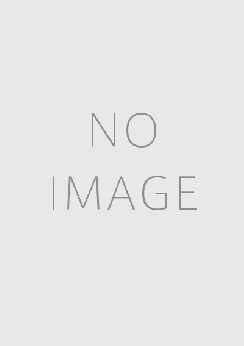
建築技師という生き方
価格未定
刊行日:2024/06/13
ランキング
-
1
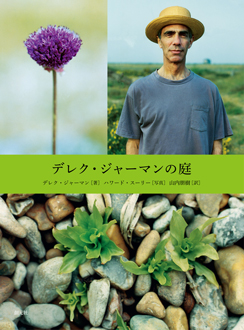
デレク・ジャーマンの庭
定価:4,180円
刊行日:2024/04/09
-
2
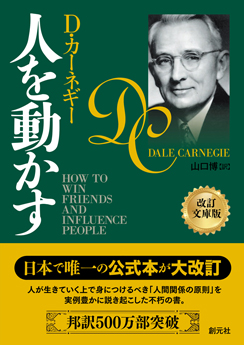
人を動かす 改訂文庫版
定価:880円
刊行日:2023/09/04
-
3
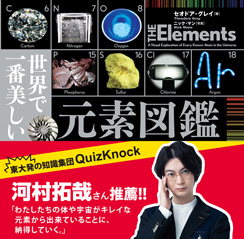
世界で一番美しい元素図鑑
定価:4,180円
刊行日:2010/10/21
-
4
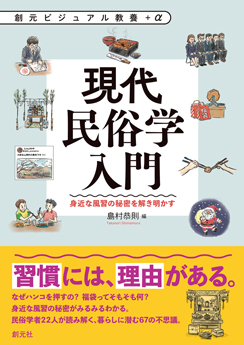
現代民俗学入門
定価:1,980円
刊行日:2024/03/11
-
5

世界でいちばん美しい こども元素ずかん
定価:2,640円
刊行日:2021/04/15
イチ推し!
-
シリーズ再開!「あいだで考える」
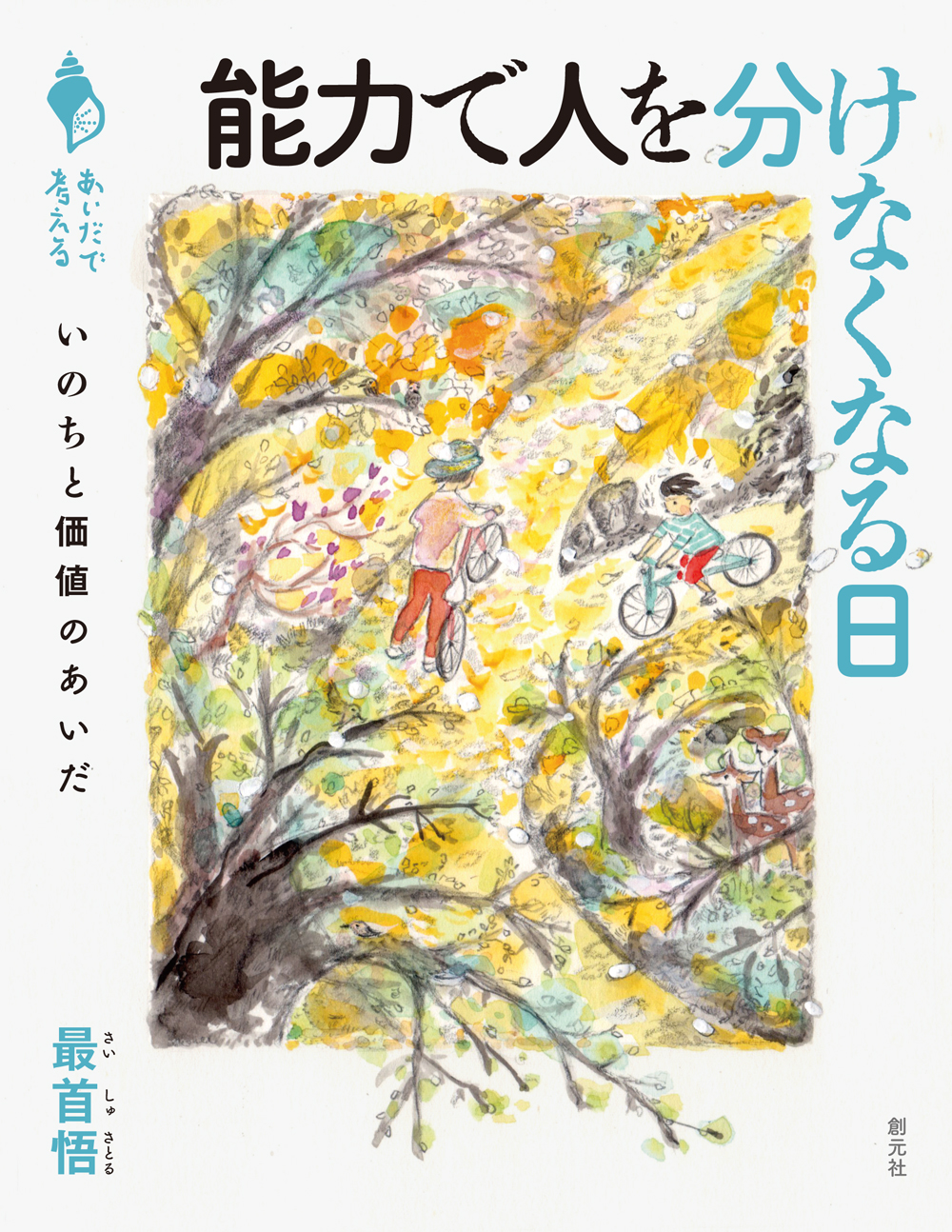
能力で人を分けなくなる日
定価:1,540円
刊行日:2024/03/25
-
3/23毎日新聞書評掲載
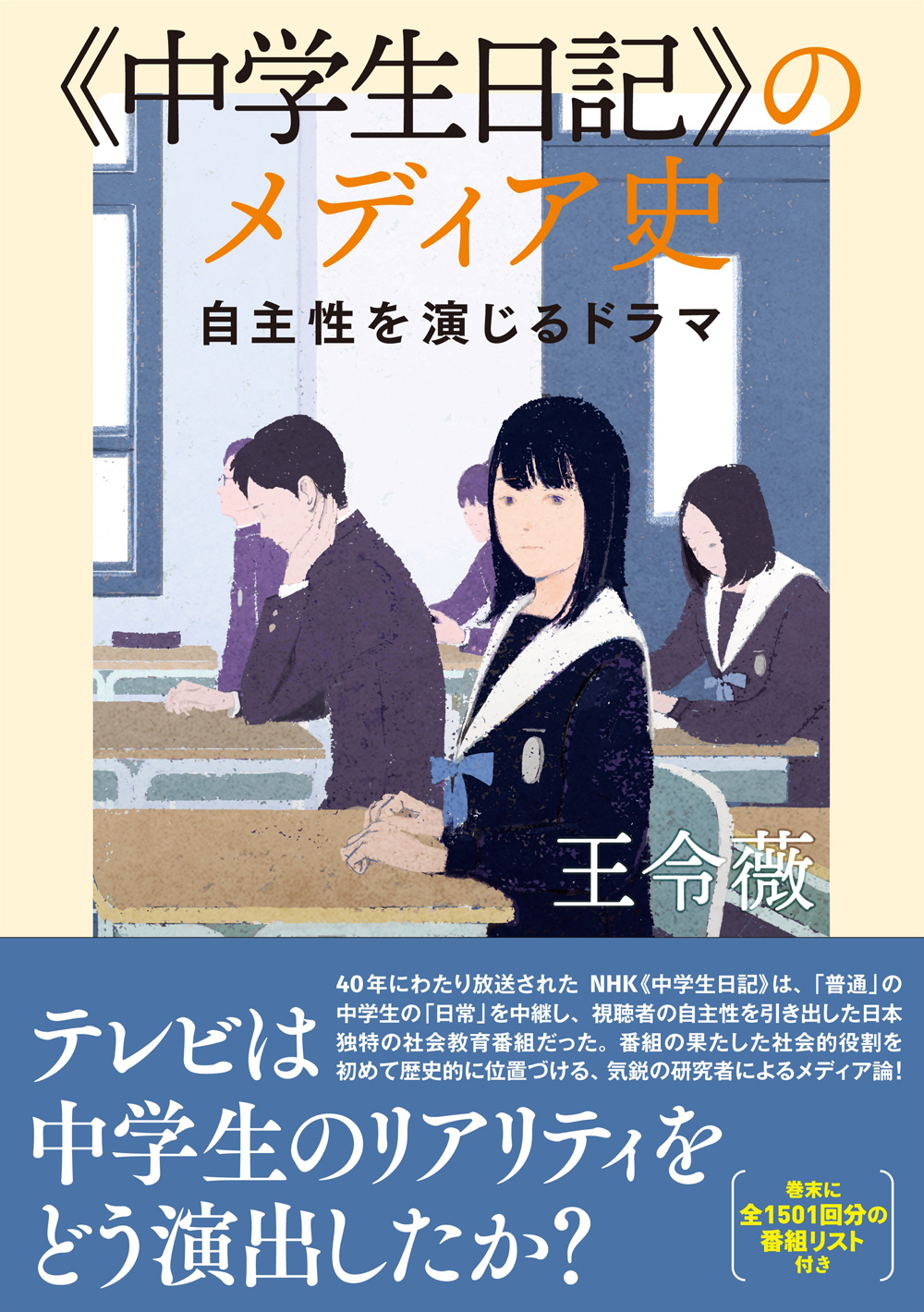
《中学生日記》のメディア史
定価:3,850円
刊行日:2024/02/14
-
改訂版刊行!
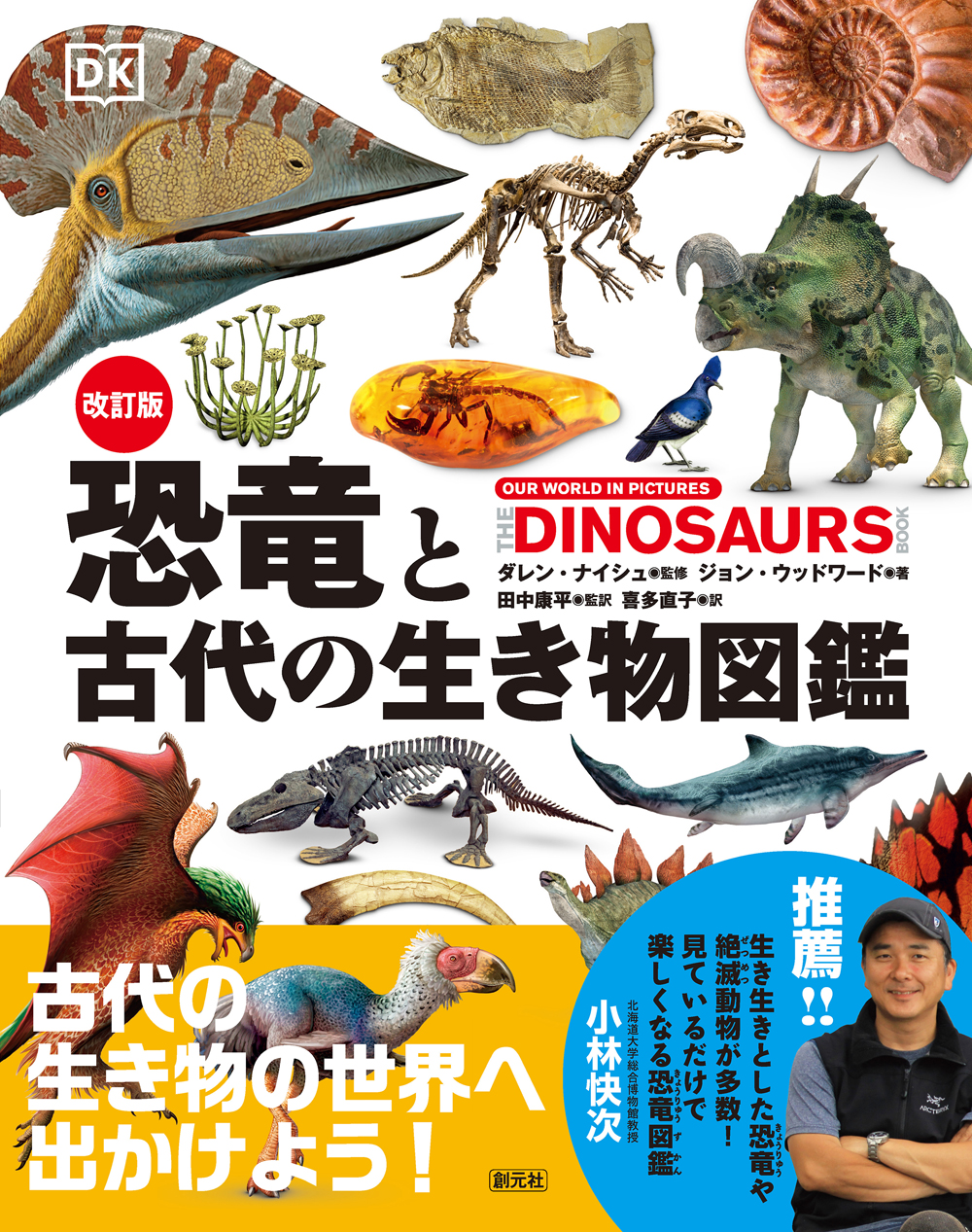
改訂版 恐竜と古代の生き物図鑑
定価:2,970円
刊行日:2024/03/25
-
<4/22up!>最新note記事
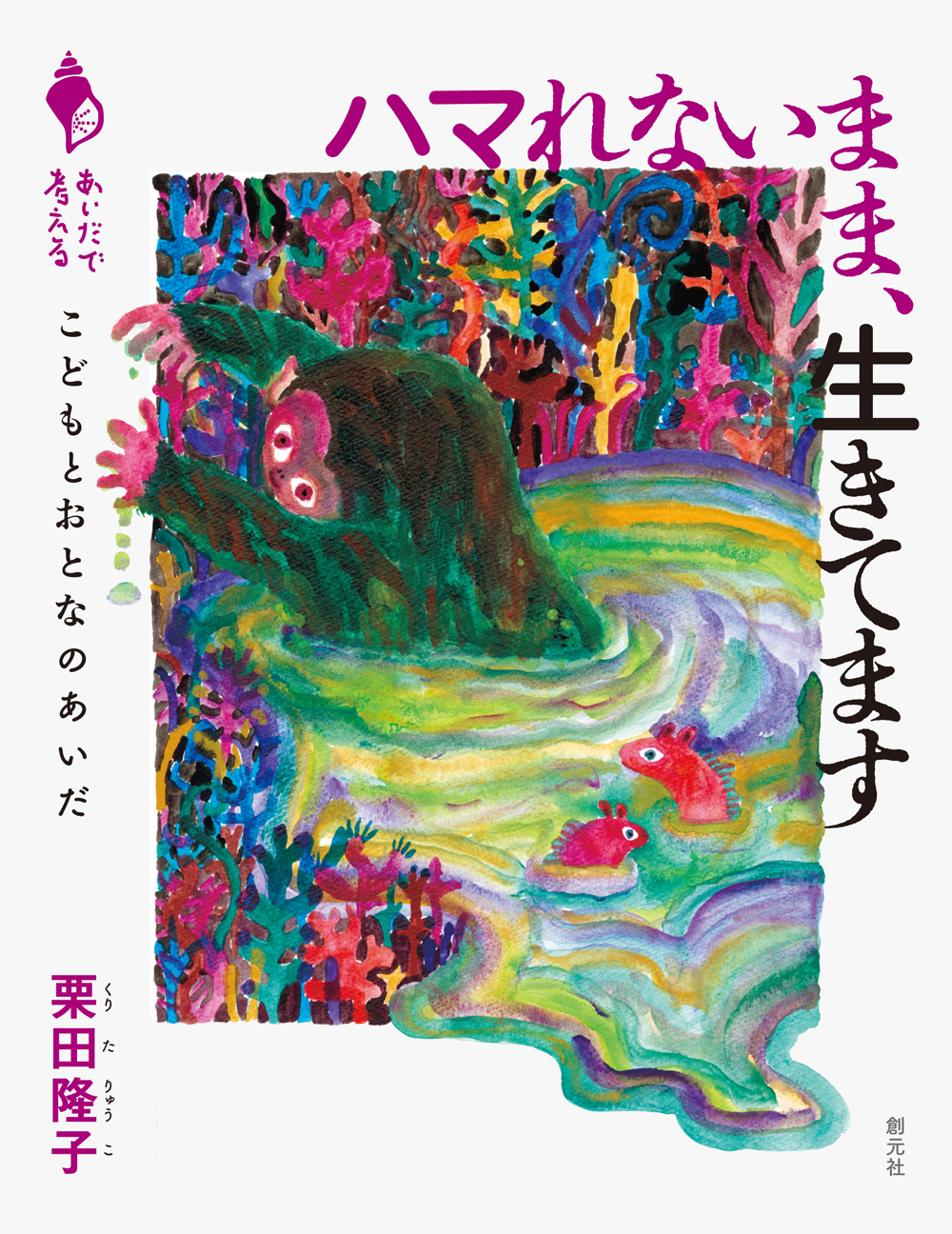
『ハマれないまま、生きてます――こどもとおとなのあいだ』の「はじめに」を公開
※「note」に移動します
-
まもなく開催セミナー情報
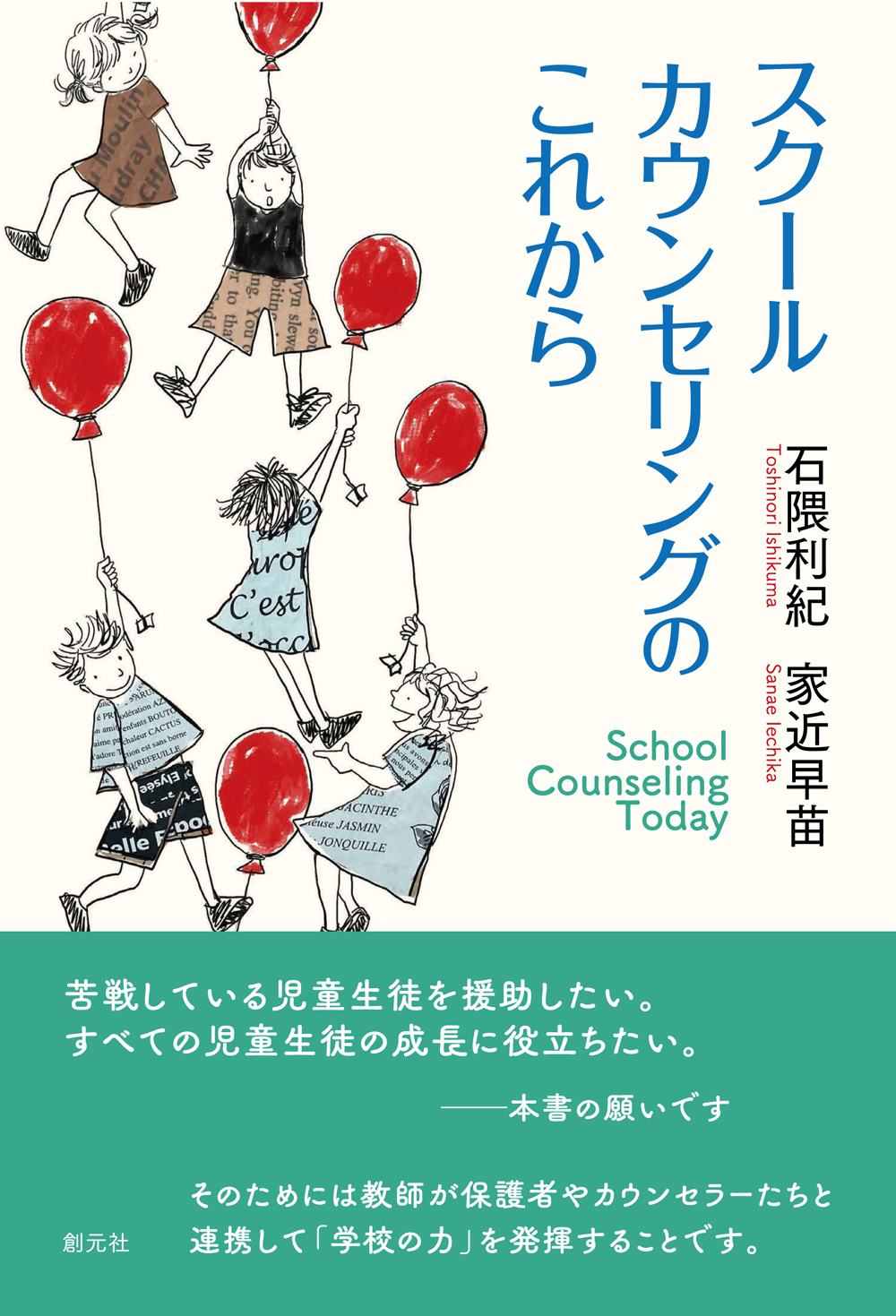
【オンラインセミナー】スクールカウンセリングのこれから、スクールカウンセラーのこれから
2024/4/27開催※別サイトに移動します
特集一覧
創元社オンラインショップの特長

送料無料
会員様は一点から送料無料(クレジット決済時)。

誕生日クーポン
会員様の誕生月にバースディクーポンをプレゼント!(入会翌月以降の誕生月にクーポンを発行いたします。)

特別販売
会員様限定!訳アリ本先行販売など、特別販売へご招待!

当日出荷
正午までのご注文で当日出荷(土日祝日除く)。
- 新着情報
-
セミナー・イベント 2024/04/24 【7/19、7/26、8/2】オンライン研修会「養成課程では学べなかった心理職の仕事(全3回)」 お知らせ 2024/04/17 システムメンテナンスによるサービス一時休止のお知らせ(2024年4月22日(月)AM1:00~AM5:00) お知らせ 2024/04/16 「書物復権」2024復刊書目決定 セミナー・イベント 2024/04/11 【5/21】オンラインイベント「現代民俗学のはじめかた~石の不思議からネットロアまで~」