| ← トップページへ | ||
| ← 前へ | 「古書往来」目次へ | 次へ → |
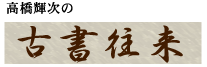 |
 |
| 7.出版社の懐かしき空間 |
前回、取り上げそこなった本から始めよう。すぐれた文芸評論家、作家である竹西寛子さんの随筆集『虚空の妙音』(平成15年、青土社)である。 河出では杉森久英、山口瞳、古山高麗雄氏らと同じ編集室にいた時期がある。 筑摩では、詩人の會田綱雄、吉岡実、入沢康夫氏がいたという。入社早々、中村光夫、臼井吉見、平野謙氏の各々500枚くらいの書き下ろし『現代日本文学史』を担当させられ、毎日のように3氏を訪ね、2、3枚でもできあがった分をもらって帰る日々だったとふり返る。まだコピー機もなかった時代のことだ。 出版社の空間といえば、私はこの正月、もう1冊、山田稔氏の旧作『特別な一日』(昭61、朝日新聞社)を夢中になって読了した。これは最近平凡社ライブラリーでも新版が出たが、私は昨年、古本を通じて知己を得た読書家の方から幸運にも元本を贈っていただいたのだ。 元々は「VIKING」に連載されたものだが、山田氏が幼少に出会った赤本の思い出から始まり、各々の長いエッセイが、氏の20、30歳代に読んだ友人の本や自身の著作、翻訳にまつわる当時の人間関係や風景などを詳細に回想してゆく、陰影にとんだ魅力的な文章群で、出版時にどうしてすぐ読まなかったのか悔やまれるくらいだ。全編を通して「記憶の不確かさ」もテーマとなっている。 中でも「わが書の来歴」は、氏の処女作『スカトロジア』(昭41、未来社)出版までのいきさつと、その後の本の運命までが詳しく描かれていて面白い。 氏は昭41年に未来社の旧社屋を訪ねたが、「二階建ての古い日本家屋で、内部は出版物がうず高く積み上げられ、その間をすりぬけるようにして通りぬけて暗く狭い急な階段を上ると、そこに応接室とは名のみの、椅子と小さなテーブルの置かれた空間があった。これが未来社か、と私はその外観の貧しさにむしろある種の畏敬の念を覚えながらあたりを見回した」と書いている。 出版社のイメージと実際の社屋の印象との落差にとまどう著者はけっこう多い。私もこれを読みながら、創元社の旧社屋を懐かしく思い出したものである。 |
 |
| ← 前へ | 「古書往来」目次へ | 次へ → |
| ← トップページへ | ↑ ページ上へ |