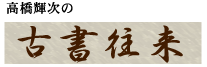再び、中村氏の回想に戻ろう。
氏は『クラルテ』の大世帯に嫌けがさし、23年10月、『反世代』を創刊。詩、批評、小説を載せる理想通りの総合誌で、石版刷りの表紙にしたが、これは2号で終刊する。その後、西本、伊勢田を中心に『幻想』『CLARTE』も出る。昭和24年から、小林武雄氏が編集長の『神戸春秋』に中村、伊勢田が記者として入り働く。その後、昭和25年秋に広田善緒が編集発行人になって創刊した『MENU』に参加したが、そこでも自分本来の詩を見つけることはできなかった。伊勢田氏によれば、『MENU』はB5判八頁、アート紙で、500部位刷ったという。『神戸春秋』が赤字になり、今度は三宮楽天地15号館にある「兵庫県重要産業新聞」の編集長となったが(伊勢田氏も記者として入社)、昭和27年末に結婚。それまでのやくざな生活と訣別し、家業の金物店を継いだ。『MENU』を離れ、『輪』を伊勢田、山本、貝原の四人で創刊したのが昭和30年5月であった。雑誌名は、伊勢田氏の提案で即決した。
『輪』60号(1985)で、氏の詩集『詩人の商売』(1984年、蜘蛛出版社)が第18回日本詩人クラブ賞を受賞した報告がなされ、足立巻一氏が「中村隆のこと」を書いている。中村氏は同人の詩集の解説や長年続けている神戸新聞の詩集評でも「さまざまな詩人の美点を鋭く見つけて暖かくはげまして」きたが、おべんちゃらなど金輪際口にできない男で、「『輪』の結束が固くて三十年も持続したのには、中村のこうした実直な人柄に負うところが大きいと思う」と述べている。そして、中村を「都会の農民」と寸評し、それが好きでたまらぬのだ、とも。さらに、その詩は「単なる泥臭さ、リアリズムではない。モダニズムやさまざまな詩法を早く潜っている」と評し、この賞で全国的にも評価されたことを「うれしくて自慢したい気分だ」と熱く祝福している。足立氏は同人ではないが、『輪』の客員的存在だったようで、時々詩やエッセイを寄せている。(※3)
※3 例えば、61号には「足立巻一追悼」集もあり、桑島玄二氏が足立氏の知られざる出版エピソードも記している。足立氏は出征した中国戦線で書きためた詩を集め、第一書房で出すことになっていたが、その内容が勇壮なものでなかったせいで実現されなかった。また、初めての著書『宣長と二人の女性』は、神戸詩人事件の犠牲者の一人、佃留雄が出獄後、東京へ出て兄の経営する小出版社の営業を手伝っていたが、思いついて詩人仲間の足立さんに依頼したいきさつがあり、戦時中に出たという。(佃氏は戦後、雑誌『デカメロン』の編集長にもなっている。)これらは私には初耳であった。また62号でも桑島氏は、昔の詩人仲間の半田透の追悼記の中で、足立氏の『親友記』の書出しに出てくる、小学二年の折出会った最初の親友、川崎藤吉は、半田透のことと明かしている。川崎は半田が戦時中勤めた軍需工場の会社名であり、藤吉は、半田が小学校を出てすぐ勤めた画材店の呼び名だという。足立氏がプライバシーに配慮したのだろう。私はこの本は殆ど実名で書かれたものと思っていたので、これを知り、再検討が必要だなと思った。 |