| ← トップページへ | ||
| ← 第55回 | 「古書往来」目次へ | 第57回 → |
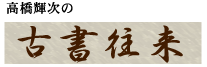 |
 |
| 56.中村隆と『輪』の詩人たち ─ キー・ステーションとしての古本屋、そして金物店 |
さて、『輪』を読んで、とくに私が注目したのは創刊から長年、編集発行人であった中村隆氏とそれを引継いだ伊勢田史郎氏のエッセイである。(この二人が両輪の輪のように雑誌を長い間支えた。) 氏の文学との出会いは昭和17年秋、中学三年の頃、神戸三中(現・長田高)で体操教師をしていた中村東角先生(当時「ふあうすと川柳社」同人)から俳句の教示を得て以来という。高名な俳人の句集をいろいろあげて、(……おそらく買い求めたのだろう。およそ百冊あまりの句集や、歳時記や、長田神社のそばの古本屋で買った古い「雲母」数十冊も、すべて空襲で灰になった。)と書いている。ここで早くも古本屋が登場する! 文学的出発が俳句や短歌から始まった詩人は少なくない。その後、地理教師をそそのかして一冊切りの同人雑誌『雄叫び』を出す。退学寸前に東京農大へ進学したが、戦時中で授業は殆どなく、『俳句と旅』に属しながら、いろんな俳句雑誌に投句した。しかし戦争末期に東京大空襲で目撃した「悲惨な情景は俳句で書き現わせなかった。」そして「敗戦の日に二、三句書き留めたきり、俳句とは絶縁した。」と記す。 詩との出会いは、ある日、下宿の円本(改造社版?)の中にあった野口米次郎、ホイットマン篇に接したのが最初であった。昭和21年2月(私が丁度生まれたときだ!)、神戸に帰り、バラックの建ち並ぶ街を憑かれたように歩き回った。 ※2 伊勢田氏の文によれば、正確には間口三間ばかりの小さな貸本屋であった。 |
引用続きで恐縮だが、ごらんのように、三人もの詩人たちが戦後すぐに古本屋をやっていた事実に驚く。中村氏は出歩いてばかりいる店主に代って「火の鳥書房」の店番を引き受け、狭い壁面の棚に非売品で置いてある吉田一穂や北園克衛、春山行夫、西脇順三郎などの宝石のような詩の本を読み漁ったという。この小さな店に広田善緒や湊川温泉からの帰りの竹中郁らが立ち寄った。 |
|
 「火の鳥」表紙(コピー) |
『火の鳥』は仙花紙の薄っぺらい、赤い題字の表紙であった。この雑誌を通して多くのキラ星のような先輩詩人たちと出会うが、その後、小林氏から「火の鳥」の下部組織を作らないかと話があり、山本氏とともに、初めて詩を書こうという若い人たちを結集し、『クラルテ』を創刊する。ガリ版刷りで三色刷り、当時では豪華版だった。研究会や講演会も催し、会員は150名を超えたという。 |
そこで費用負担をまかなうため、中村氏も山本氏の協力を得て自宅の倉庫を改築し、古本屋「クラルテ書房」を開業する。「セリ市に出掛けては、値を度外視して詩書をセリ落し、神戸の古書界ではたちまち有名になった。」とある。しかし、その資金は寝たままで、夜ともなれば毎晩会員の誰かれを引きつれ、売り上げ金を懐に新開地を飲み歩いたため、一年もたたずに倒産した。 ここで、『輪』の創刊同人の伊勢田史郎氏が、同誌に断続的に連載した「私的なノート」に目を向けよう。その(3)(1977)で、丁度同じ時期に中村氏と密に交遊のあった氏がクラルテ書房のことを証言しているからだ。 |
|
| << 前へ 次へ >> | |
| ← 第55回 | 「古書往来」目次へ | 第57回 → |
| ← トップページへ | ↑ ページ上へ |