| ← トップページへ | ||
| ← 第47回 | 「古書往来」目次へ | 第49回 → |
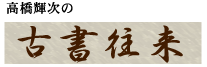 |
 |
| 48.織田作・青山光二らの友情と世界文学社・柴野方彦 |
さて、本書は、京都での学生時代や戦後すぐの場面が主に回想されているのに、記憶が驚くほど正確で、まるで今、眼前の出来事のように、生き生きと詳細に再現されているのが見事だ。一例にすぎないが、織田作の担当編集者だった各社の人々の名もすべてフルネームで記されている。 まず瀬川健一郎は本書の紹介によると、東大文学部を出て大阪毎日新聞社に入り、「小学生新聞」の編集長を長く勤めた人。昭和14年、織田と宮田一枝の結婚式の媒酌人を勤めている。それまでにも、織田が京都の酒場「アルト・ハイデルベルク」で女給をしていた一枝さんに一目惚れし、その酒場の二階に寝泊りしていた彼女を脱出させるため、喜んで協力したのも瀬川である。夜更けに彼が調達してきた梯子を壁に立てかけ、彼女がつたって降りるのを織田と二人で手伝ったというエピソードが語られている。こんなのはほんの一例である。 白崎については、本書でもわざわざ一文を設けて書いている。彼が昭和19年に結核で亡くなったとき、実家の敦賀市での葬儀に出かけた折のことを回想している。織田を初めて文学の道に誘い込んだのが白崎のようだ。白崎も宮田一枝のいる「アルト・ハイデルベルク」に通う織田作に連日つきあい、青山氏とも東京で一年以上同居して氏の恋愛問題にも徹底的につきあった。敦賀の旧家の出で、育ちのいい、行儀のいい人だが、異常につきあいのよい性格だったという。 |
青山氏と織田作の深い交友の一部始終は前述の『青春の賭け』に詳細に描かれているが、本書でも「死に水をとる」という短文で、織田作が息を引きとった翌朝、声には出さずその言葉をつぶやいて以来、三十年余りかけた、その具体的実践の跡を記している。まず、中央公論社の選集五巻に全巻の解説を書き、年譜作成には瀬川氏の協力を仰いだ。次に、現代社の『織田作之助名作選集』(昭30〜31)、新書シリーズ14巻の編纂。 |
|
 「夫婦善哉 船場の娘」カバー |
このうち、私が古本で持っているのは『夫婦善哉 船場の娘』位のものである。8篇が収録されており、これにも青山氏が解説を書いている。口絵の両作品の東宝映画のスチール写真が今では貴重かもしれない(とくに後者の岸恵子が!) |
織田作の作品を世に遺すことにここまでねばり強く献身されるとは! 想えば織田作はよき友人達に恵まれた、幸せな作家であった。よほど彼が人間的にも魅力のある人だったからだろう。本書でもそのことは随所に伺われる。彼の人生そのものがドラマティックで、一編の小説みたいにも思われる。 本書で青山氏は深くつきあった氏でないと気づかぬような織田作の側面もいろいろ報告している。彼の恋愛相手に共通するのが、不良っぽい、どこかニヒルな、デカダンス漂う美人だったこと、雨が実に好きだったこと、樹木や花々といった自然の美しさには殆んど興味がなかったこと、酒はわずかしか飲まなかったこと、小説の結末のオチが浮ばないうちは書き出せず、決ると一気呵成に書き上げるタイプだったこと、などなどである。 |
|
| << 前へ 次へ >> | |
| ← 第47回 | 「古書往来」目次へ | 第49回 → |
| ← トップページへ | ↑ ページ上へ |