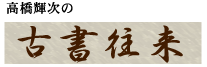彼女は新聞記者をやめ、下着デザイナーへの道を歩み出すのだが、その頃の彼女の下着観を簡潔に表現した名言を引いておこう。「いわば下着は、私にとって自分の心理を表現するタブローである。そして社会を見るフィルターでもある。私の心はまるで砂漠の哲学者のように下着をモチーフにしてしずかに沈潜していった。」と。
友人のアキ子のアパートの部屋を作業場にして彼女は仕事を始めるが、その革新的な下着観を世に問うため、まず個展を開くことにした。
その初めての会場は大阪そごうの中二階ギャラリーの曲り角の一隅、九坪の空間で、彼女の意向を受けてそごう宣伝部の人が知恵を絞り、会場としてひねり出してくれたものだった。なかなかユニークな空間の利用である。この会場構成を、おそらく記者時代に知己になった(あるいは飲み友達か?)早川良雄氏に頼んだ。彼女は「これは早川氏の傑作の一つだと私は今でも確信している。」と書いている。
周知のように早川氏(1917〜)は関西グラフィックデザイン界の大御所で、近年では大阪人には例えば、明るい柔らかいタッチで描かれたパステル画の女性像を全面に用いた、京阪百貨店のポスターでよく知られていよう。その空間は、といえば、真暗な壁面に囲まれ、赤、黄、青のスポットが照り、天井の黒い角材からいろんな下着がぶら下げられて空中に浮いている、といったものだった。何も知らずに会場をのぞいた観客はさぞ度肝を抜かれたことだろう。 |