| ← トップページへ | ||
| ← 前へ | 「古書往来」目次へ | 次へ → |
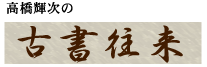 |
 |
| 31.大阪の知られざる古い詩人たち ─ 大西鵜之介と藤村青一 ─ |
今年春の京都の古本祭りは初日に出かけ、福田屋書店のコーナーで、一寸気になるタイトルの函入りの詩集を見つけた。大西鵜之介著、叙情歌集『薔薇の騎士』(叙情歌社、大正14年)である。 |
|
 ビニール包みだったが、つい中をのぞきたくなって封をとって取り出すと(困るなあ・・・)、本体表紙にバラの花を口にくわえたトランプのクイーン(?)を上下に逆様に配した意匠が現れ、頁を開くと、口絵に伊藤杜詩夫という未知の画家(装幀も同人)の「悲しき十三時半」と題する、三日月の下弦に乗った若いピエロの男女が接吻している図を可愛く描いた白黒の版画っぽい、世紀末風の絵が目に入ってきて、瞬間、気に入ってしまった。 ビニール包みだったが、つい中をのぞきたくなって封をとって取り出すと(困るなあ・・・)、本体表紙にバラの花を口にくわえたトランプのクイーン(?)を上下に逆様に配した意匠が現れ、頁を開くと、口絵に伊藤杜詩夫という未知の画家(装幀も同人)の「悲しき十三時半」と題する、三日月の下弦に乗った若いピエロの男女が接吻している図を可愛く描いた白黒の版画っぽい、世紀末風の絵が目に入ってきて、瞬間、気に入ってしまった。 |
|
 口絵「悲しき十三時半」/伊藤杜詩夫 |
|
それに奥付を見ると、発行所住所が「大阪市南区難波新地二ノ十二」となっており、大阪発の出版だ!著者の住所も「南区瓦屋町二番丁五十番地」で印刷所はすぐ近くの十二番地、山田文化堂とあり、おそらく自費出版であろう。 この歌集の函の題箋(だいせん)はタテ組だが、本文はすべてヨコ組で朱色のケイで囲んだ頁の中に四首ずつ収められていて、この時代の本としては大胆で珍しい組み方だろう。(歌にローマ字が時々出てくるからでもあろうが)内容は、おそらく二十代の著者の、実体験とフィクションを織りまぜた恋愛、とくに悲恋の情調を様々な場面で唱ったもので、若者特有のモダンなロマンティシズムといった雰囲気が濃厚である。古き良き時代の道頓堀や京都祇園などを舞台にしている。 「とある夜とあるカフェの/石卓に/コーヒ茶碗の並びし思い出」 といったものである。 さて、この大西鵜之介という著者だが、調べればすぐに略歴位分るだろうと思い、まず『近代文学大事典』や最近出た『大阪近代文学事典』などを見たが、立項されていない。詩歌書専門の石神井書林目録のバックナンバーを繰ってみても一冊も出てこない。 |
 「奇妙な本棚」函 |
そこで私は、大阪、十三の詩人、故清水正一の本や小野十三郎『奇妙な本棚』(第一書店、昭39)収録のエッセイを要約しつつ、戦後すぐの大阪の小さな出版社のことを紹介しており、大西の名も何度か文中に出てきたのだ! |
小野は昭和22年、『詩論』を真善美社から出すが、誤植も多く完全なものにして残しておきたかったところ、出版社がつぶれ絶版になっていた。 |
|
なお、藤村兄弟の青一氏については、同じ所で小野も少し語っているが、前述の小野原氏が古本で見つけて進呈して下さった河津武俊著『秋澄』(講談社、昭63)に一章とって詳しく登場している。 |
 「秋澄」表紙 |
この本自体、興味深いが、今は簡単に青一氏の話に焦点を当てると、氏も明石の生れで、昭和5年関西学院大を卒業し、義兄のラシャ問屋で働いていた氏は麻生路郎主宰の川柳会に参加し、そこで岡田(号・某人)と出会い、陰(岡田)と陽(青一)の正反対の性格でひかれ合い、以来無二の親友となる。岡田が放浪から大阪へ戻ってきた折、何かと面倒を見たり、晩年に至るまで親交を続けている。 くらやみに酔い撒きちらし杖おどる なお、兄の雅光氏も、以前見た古本目録によれば、昭和23年、詩集『葡萄の房』を小野十三郎の序文、鍋井克之の装幀で出している。出版社は不明だが、おそらく自社の不二書房からだろう。 なお、中之島図書館で調べてもらったところ、大西の『薔薇の騎士』は大阪女子大図書館と国会図書館しか所蔵してないそうである。 |
|
+++ この原稿を書いた直後にふと思いついて石神井書林目録の最近号を繰ってみると、雑誌の項に、『詩文化』18冊一括とバラで一冊、14号(昭24年9月)が出ているではないか。むろん、前者は高くて買えないので、後者の一冊をすぐに注文した。 さて、私が他に注目したのは表紙裏に載っている不二書房(阿倍野区清明通一の四一)の出版広告である。 |
(追記) |
|
| 本はB6判100頁程の並製フランス装だが、紙はりっぱな厚い上質紙。田村孝之介の葉鶏頭とトンボを描いた単彩スケッチが表紙を飾っている。口絵に著者近影写真があり、和服でペンを握った青一氏が俳優かと見まがう程のハンサムな顔でこちらを見つめている。まだ三十代始めの頃だろう。 |  「詩人複眼」口絵 著者近影より |
序文はまず川柳の師、麻生路郎の面白い”序文考”を含んだ一文。次に大阪出身の先輩詩人、百田宗治の一寸辛らつな文章、跋には大阪の詩友、吉川則比古による青一氏とのつきあいと好意的に著者像を語った一文が添えられている。(吉川も戦前の大阪で全国向けの詩誌『日本詩壇』を長らく編集していた詩人。) |
|
| ← 前へ | 「古書往来」目次へ | 次へ → |
| ← トップページへ | ↑ ページ上へ |