| ← トップページへ | ||
| ← 前へ | 「古書往来」目次へ | 次へ → |
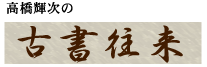 |
 |
| 17.黒瀬勝巳、その人と詩集 |
黒瀬勝巳は知る人ぞ知る詩人で、一般には殆ど知られていないだろう。 にもかかわらず今回紹介しようと思ったのは、黒瀬氏の本職が関西(京都)の出版社の編集者だったからで、私にはとくに身近に感じられるからだ。むろん面識はなかった。 しかし、遺稿詩集『幻燈機のなかで』(編集工房ノア)巻末の年譜を見ると、生れも私より一年前の昭和20年で、42年同志社大学法学部を卒業、京都の教学社に入社し、併設の世界思想社の編集業務に従事したとある。 |
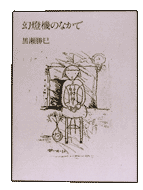 「幻燈機のなかで」表紙 |
 「ラムネの日から」表紙 |
私が大学卒業後一年間勤めた銀行をやめ、創元社に幸運にも入社したのが確か昭和44年なので、ほぼ同時代に同じ関西で編集者をやり始めたことになる。 黒瀬氏は昭和55年に退社するまで同社で13年間働いている。その間に仲間と同人誌誌『櫓』を七号まで刊行、『ノッポとチビ』にも参加し、昭和53年、処女詩集『ラムネの日から』(編集工房ノア)を出している。 関西の新世代の旗手として将来を期待されていた詩人だが、惜しいことに昭和56年、36歳の若さで自死されている。 |
私が彼のことを知ったのはまだ半年位前のことで、古本で見つけた河野仁昭氏の『戦後京都の詩人たち』(平成12、「すてっぷ」発行所)を興味深く読んだ折に、河野氏が編集していた『ノッポとチビ』の同人の一人として割に詳しくその詩と人物像を紹介していたからである。 中でもそこに最初に載せた「文庫本としてのおふくろ」が面白く、いかにも本好きの編集者らしい発想だなと印象深かった。 せっかくの機会なので、一部だけ引用すると、 「おれはおふくろをめくり/おれはおふくろをくりかえし読む/いまではおふくろは文庫本くらいに小さくなり/おれの尻ポケットにも楽にはいる ―(二連省略)― おふくろはおれの尻ポケットで/思想もなく眠る/週刊誌を読まなかったおふくろ/だからといって/おふくろは角川文庫なんかじゃないよ」 というもので、最後のセリフが実に効いている。 |
 「戦後京都の詩人たち」表紙 |
むろん、これは大衆化以前の角川文庫のことではない。 その後私は河野氏にお便りした際、思いがけず贈っていただいた氏の『詩のある日々 ― 京都』(京都新聞社)にある二篇の黒瀬氏の追悼文を読んで、より詳しく彼の生い立ちや人間像を知ることができたので、要約して紹介させていただこう。 河野氏も詩人で評論家だが、当時同志社大で資料室長をしておられ、黒瀬氏の姉がそこで仕事を手伝った関係で、在学中の弟とも知り合った。 卒業の折に相談にやって来て、どうしても出版の仕事をやりたいので、すでに採用が決まっていた大阪の会社を辞めてきたという。このへんも私と似ている。 河野氏が紹介した出版社に入社できると、少年のように喜んでいた。 数年後、二度目の相談では、大学ホールでの簡素な結婚式のセレモニーに立ち会う仲人役を頼まれた。その折、黒瀬氏は法学部の卒業生なのに「法律用語さえ口にしたことがなかったように思う」と書いている。いかにも詩人らしいではないか。 氏が中三の時、母親が死んだが、末っ子で甘えん坊のはずの氏は人前で泣かず、一人裏山などへ行って泣いて帰ってきた、と姉さんから聞いている。 以来、<母親>は彼の抜きさしならぬ詩の主題であり、『ラムネの日から』を出版した折、出来たての詩集をバイクで届けに来てくれたが、「臍の緒が切れとらんのや、こんなふうに集めてみたらそれが目だつんや」と繰り返し言ったという。 氏の詩作へのこだわりについても河野氏は紹介している。原稿を直接届けにきては、「最低一度は、その原稿を直しにくるか、改稿してもってきた」が、多くの場合、一字か数字の書き直しだった。 氏は亡くなる三日前に珍しくネクタイ、スーツ姿で現れ、「例になくことばまで改まった調子で、就職や結婚の仲人のことについて礼をいって、わたしを面喰らわせ」た。突然の死を知らされ駆けつけた祭壇の前で「わたしは発作的に、目を開いて大袈裟に泣いた」と河野氏は記している。 氏の編集者としての仕事がどんなものだったか知りたいが、それに関する情報は今のところ全くない。ただ、『ラムネの日から』には、「校正」と題する編集者ならではの短い散文詩が収められている。それは、 「まっ赤になってしまった校正刷を目の前に/ほとんど狂いそうになる まいにちまいにち/生きるや死ぬをやっても紙のうえでののたうち/で けど死んでいった活字一本一本の犬死に/のたれ死にやまい死にのかずかずを おれも/たしょうはつらい気もちでながめてきたのだ」(以下二連略) と書き出されている。 思い出せば私も仕事の初期はまだ活版の校正ゲラの、ゲタ付きやひっくり返った活字によく朱を入れたものだが、このような、いわば捨てられた活字の身になって(?)校正した記憶はない。氏は仕事にも全力を投入して燃え尽きてしまったのだろうか。(むろん、死の原因など本人にしか分らないが) 私が黒瀬氏の詩集を探していると訴えると、今回も古本仲間の津田氏がインターネットで見つけて下さり、二冊とも譲って下さった。(第一詩集の方は希少なので、わざわざコピーした本文と表紙を巧みに製本して!) 『幻燈機のなかで』には「ニセモノ好み」「猪木、マザーグースを唄ってくれ」という軽妙でユニークな視点から書かれたエッセイも収録されており、エッセイストとしての才能も充分あったのにと残念に思う。 巻末に大野新氏の心のこもった痛切な「黒瀬勝巳に」が付されているが、その中で天野忠の「黒瀬の詩集はスマートだし、軽いニヒリズムがある」という的確な評言を紹介している。 私は、個人的には第一詩集の方が好きである。ことば遊び的な詩が多い遺稿詩集に比べ、おふくろやわが子へのやさしいまなざしが感じられる詩が多く含まれているからだ。それに自装だそうで、タイトルにふさわしい幻想的でノスタルジックな装画を使った、かわいらしい詩集である。 いつかこの本の実物と死後もう一冊出された『白の記憶』もぜひ手に入れたいものである。 |
|
| ← 前へ | 「古書往来」目次へ | 次へ → |
| ← トップページへ | ↑ ページ上へ |