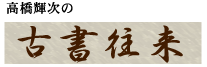今回は古本の話というより、いささかノスタルジックな私の回顧談になってしまうことをあらかじめお許し願いたい。
その回想は、新刊の一冊の文芸雑誌を読んだことから始まる。たまたま、ふだんあまり読まない2月の文芸時評を朝日、読売紙で拾い読みしていたら、『新潮』3月号に載った四方田犬彦氏の「先生とわたし」という400枚原稿一挙掲載の長篇評論が力作として紹介されていた。この”先生”とは、英文学者であり、脱領域の知性の持ち主でもあった故・由良君美氏のことというではないか。私はこれはぜひ読まねば、と思い、早速、翌日駅前の本屋へ走ったが、『新潮』は売り切れと見え、他の二、三店ものぞいたが、置いていなかった。あきらめかけた次の日、梅田の紀伊國屋でわずかに一冊、残っていたので買い求めたが、危ないところだった。いずれ、単行本としても出るだろうが、一刻も早く読みたかったのだ。ひょっとして今月号の『新潮』はこれを読みたい人がこぞって本屋へ走ったのかもしれない。
早速、行き帰りの車中や寝床でも夢中になって読み耽り、さすがに単行本一冊分あるので、四、五日かかってようやく読み終えた。久しぶりに知的興奮を存分に味わった、圧倒的読書体験であった。
さて、本文は、1990年8月、四方田氏が所用で神戸に滞在中、時間つぶしに入った喫茶店で偶然手に取った新聞で、氏の先生であった由良君美氏の死去の報を知り、急遽東京へ戻って由良家にお焼香に出かけるところから始まっている。葬儀は行われず、遺言によってワーグナーの「ローエングリン」が三日間流されていた。
「第1章 メフィストの知」では、弟子であった四方田氏の視点から由良氏を回想し、氏が東大二年生の折、1973年4月から始まった教養学部や大学院での由良氏の独創的で刺激的な講義やゼミの様子を描く。例えばその一つ、「メルヘンの論理」は、イギリス文学をユングに基づく神話原型論やロシア・フォルマニズム以降の記号学などの広範な理論を駆使して分析してゆくもので、圧倒される。その折の由良氏の風貌を引用すると、「長い髪をオールバックにし、広い額と優しげな眼差しをした人物で、パイプを加え、ベージュ色の背広を着ていた。その一挙一動の優雅さに、先ほどまで雑談をしていた学生たちはたちまち静かになった。」とある。
「第2章 ファウストの来歴」では、編年体で由良氏を知る弟子たちの証言や著作から窺い知れる氏の肖像を描く。氏の幼少からの読書体験や学問的歩み、著作活動が詳しくたどられてゆく。
「第3章 出自と残滓」では氏の父方、母方の履歴の紹介がなされている。父の哲次氏は奈良に生れた著名な歴史哲学者で、若き日、ドイツに留学し、『象徴形式の哲学』で有名なカッシーラの教えを受けたが、帰国後はナチズムや国策に沿った哲学関係の本を数多く出版した。一方で出自と関係のある南北朝や、邪馬台国に関する研究も続け、浮世絵を中心とする日本美術のコレクターとしても有名で、死後その多くが奈良県立美術館へ寄贈された。興味深いのは、三重の上野中学で一級下であった横光利一とは生涯深い親交があり、横光の『旅愁』に資料を提供し、モデルともなったという。君美氏はその父に愛憎交々の複雑な感情を向けたが、父からは芸術への憧憬を受け継いだ。父親に欠けていたのは、君美氏が生涯もっていた、ロマン主義者としての諸学の礎にある、ポエジーである。母・清子は、東京師範学校で国語学を教えた吉田彌平の娘で、書道に長け、文学の書物好きであった。その聡明で優しげな表情はそっくり由良氏に受け継がれている。由良氏の『言語文化のフロンティア』(昭50、創元社)のトビラ裏には「母の思い出に」という印象深い献辞がある。
「第4章 ヨブの債務」は由良氏の1980年代の足跡と氏が61歳で死去するまでの歩みを四方田氏とのつきあいや二人の葛藤を中心に描いている。四方田氏は駒場の大学院終了後、韓国の大学で教えたり、ロラン・バルトの映像記号学を用いて映画論や漫画論を精力的に発表するようになる。一方、由良氏は1983年、駒場の英語科主任教授になってから、氏の学歴がまず学習院大で哲学を学び、慶応大英文科大学院で西脇順三郎の指導を受けたという東大出身の経歴でないため、人間関係上の重圧からか、酒乱の傾向がしだいに出始める。四方田氏との間にも徐々に溝が生れ出し、ある夜は二人ともへべれけになり夜が明けるまで四方田氏を飲みに連れ回す。さらに1985年のある夜、偶然居合わせた渋谷のバアで、由良氏は四方田氏が近頃、自分の悪口ばかり言いふらしていると言い、被害妄想的になって突然氏を殴りつけるという事件が起きる。他にも誤解を受け非難される事柄があったが、四方田氏は思い当らず、悩んだ末に由良氏との訣別を決意する。由良氏は1989年、東大を定年退官後、東洋英和女子大大学院へ移る。その頃、還暦記念画文集『文化のモザイック』という432頁の大冊が刊行されるが、それには分野を超えた錚々たる研究者、詩人や画家が執筆し、以前、翻訳への意見の相違でしばらく由良氏の許を離れていた、これも博学で知られる弟子、高山宏氏も再び健筆を振っている。四方田氏も由良氏から直接、丁寧な依頼を受け、直ちに執筆した。これが氏と最後に言葉を交した電話であった。由良氏は1990年、澁澤龍彦と同じく、喉頭がんで亡くなった。「由良哲次伝」など沢山の著作の構想を抱えたまま……。
次の「間奏曲」では、教師とその弟子との関係の原理的考察にまで話が及び、由良氏が生涯敬愛したユダヤ系学者、ジョージ・スタイナーの未邦訳の『師の教え』や山折哲雄氏の『教えられること、裏切られること』(現代新書)を紹介しつつ、日本や西欧での種々のケース(例えば漱石とその弟子たちや法然と親鸞、フッサールとハイデッガー ─ アーレントなど)について考察している。
「第5章 ウェルギリウスとの訣別」では、ダンテの『神曲』の挿画を描いたウィリアム・ブレイク(由良氏も生涯、ブレイクに深い関心をもち、論文も種々書いている)の図版を分析しつつ、四方田氏もまた、由良氏を対象として書き進めながら、実は自分自身の教師像にも改めて向き合っていることに思い当る。そうして、ニーチェの『ツァラトゥストラ』中の「師とは過ちを犯しやすいものである」という一節に共感を覚えるとともに、さらにそれを「師とは脆いものである」といい直して、自分の諸々の教師体験を自己反省している。氏はこう書いている。
「私は自問する。はたして自分は現在に至るまで、由良君美のように真剣に弟子にむかって語りかけたことがあっただろうか。弟子に強い嫉妬と競争心を抱くまでに、自分の全存在を賭けた講義を続け、ために自分が傷つき過ちを犯すことを恐れないという決意を抱いていただろうか。」と。
最後の「エピローグ」では、由良氏夫人の死の報に接し、師の墓をやっと探し出し、その富士霊園の「文学者の碑」にカップ酒を振りかけ、ようやく師と和解できたと思うところで、終っている。
以上、まだ読んでない人のために長々と下手な要約を試みた。私は、本文の中途で、人間・由良君美氏の知られざる影の側面に初めてふれ、いささかショックを受けたものの、最後まで読み通すと、まるで荘厳な鎮魂曲を聴き終えた後のように、心が安まり、感動した。これは、師や弟子をもつ幾多の研究者たちに共感を与え、切実に考えさせるインパクトのある、すぐれた評論だと思う。実際、朝日紙3・6朝刊に載った鶴見俊輔氏と四方田氏の対談でも、鶴見氏がこれを「3、4日かけて読み終えたとき、率直にいって、涙がこぼれた。あれと比べられるのは、日本文学のなかでは鴎外(※1)の『渋江抽斎』ぐらいだ。隣りに並べても甲乙つけられない。」とまで絶讃している位である。
※1 『鴎外』の『鴎』のへん「メ」は「品」となる。 |